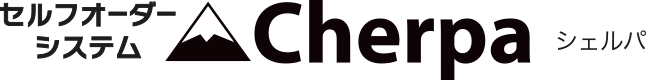2024.12.2
経営
歴史から学ぶ外食産業のこれから

外食産業は、消費者の嗜好やライフスタイルの変化に常に影響を受けています。最近では、健康志向や環境意識の高まりが顧客の選択に影響を与え、業界全体が新たなビジネスモデルを模索する必要性が増しています。 この記事では、歴史を振り返り、現在、そしてこれからの外食産業を考えていきます。
---- Table of contents -----
外食産業の歴史を振り返る
日本の外食産業は、戦後の復興と共に発展し、人々のライフスタイルの変化や社会情勢を反映しながら、常に進化を遂げてきました。
形成期(江戸時代前期〜)
外食文化の始まりは江戸時代です。蕎麦、寿司、天ぷらは、屋台で手軽に食べられることから人気がありました。 明治時代になると西洋文化が日本に流入し、外食文化に大きな影響を与えました。飲食店の数が増加したことで、外食は庶民の生活においてますます一般的なものとなったのです。
江戸時代の外食文化:ファストフードやグルメガイドブックがあった?
黎明期(1960年代)
1960年代、日本の高度経済成長とともに外食産業が芽生え始めました。この時期に外食レストランチェーンの概念が生まれ、産業としての基盤が形成されていきました。
成長期(1970~1990年代)
資本自由化を背景に、アメリカの外食チェーンが日本に進出し、国内資本も外食産業に参入しました。 ファミリーレストランやファストフードチェーンが全国に展開され、多店舗展開による業務の合理化や接客マニュアル導入によるサービス向上など、外食産業としての形が整えられていきました。 1980年代のグルメブームでは、エスニック料理やフランス料理、イタリア料理なども人気を集め、外食は特別な日から日常的なものへと変化していきました。
変革期(1990年代~2000年代)
バブル崩壊後の景気低迷により、外食産業の成長が鈍化。各社が低価格路線へシフトし、価格競争が激化しました。 テイクアウトや宅配サービスなどの中食市場が成長し、1995年の阪神淡路大震災を契機に、危機管理の重要性が認識されました。 また、1996年のO-157問題を受け、食の安全への取り組みが強化されました。
転換期(2000年代~)
BSE問題や食品偽装問題など、食の安全性を揺るがす事件が相次ぎ、消費者の信頼回復が課題となりました。 その他、健康志向、本物志向、グルメ志向など、消費者の価値観が多様化しました。
新時代(2020年〜)
コロナ禍により、外食産業は大きな打撃を受けましたが、同時に新たな変革の機会となりました。 デリバリー需要の増加に対応し、ゴーストレストランなどの新しいビジネスモデルが登場しました。
ウーバーイーツならではの仕組みを理解してデリバリーを導入!
ゴーストレストランとは?特徴と注意点をわかりやすく
食の安全・安心への取り組み
1990年代から2000年代初頭にかけて、BSE問題や輸入農作物の残留農薬問題など、食の安全性を揺るがす事件が相次いで発生しました。これらの事件は、消費者の食の安全に対する意識を大きく変え、外食産業に対しても、より高いレベルでの安全性が求められるようになりました。
消費者の声を受け、農林水産省は2005年に「外食における原産地表示に関するガイドライン」を策定。これは、外食産業が自主的に原産地表示を行うための指針となるもので、表示の対象、表示方法、表示場所などについて具体的に示されています。 これを受け、多くの外食企業は店舗メニューやホームページ上で積極的に原産地表示を実施するようになりました。
例えば、BSE問題をきっかけに、企業は肉類の原産地表示を開始し、その後主要食材についても表示する方針を掲げ、ホームページで最新情報を確認できる体制を整えるようになりました。
海外における日本食ブーム

2013年、「和食:日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを契機に、世界的に日本食ブームが巻き起こっています。
訪日外国人観光客が訪日前にもっとも期待することは「日本食を食べること」という調査結果が出ており、日本食は海外の人々にとって大きな魅力となっています。 また、海外における日本食レストランの数は、2013年の約5.5万店から2023年には約18.7万店へと、10年間で約3.4倍に増加しました。昨今は、ラーメンがその代表格として、海外の日本食市場を開拓しています。 2015年に行われたミラノ万博の日本館で、クオリティの高い日本食が人気を博し、欧州にも日本食レストランが増加したのも、きっかけのひとつと言われています。海外進出している日本食レストランは、質の高い料理と効率的な運営を両立させている点が共通しており、日本国内で培ってきたノウハウを生かして海外でも成功を収めています。
生産者との連携
近年の食の安全・安心志向の高まりや、食の多様化、そして地域活性化への意識の高まりから、外食産業と生産者の連携がますます重要になっています。
このように、日本の食文化は、外食産業の進化、食の外部化の進展、食の安全・安心への取り組み、海外における日本食ブーム、そして生産者との連携といった様々な要素によって、常に変化し続けています。
現在、これからの外食産業
2023年の外食産業の売上は、コロナ禍からの回復基調が続き、全体売上は前年比114.1%、2019年比107.7%となりました。これは、コロナによる行動制限の緩和や解除、訪日外国人増加によるインバウンド需要拡大などが要因です。特に5月以降、コロナが「5類」に移行したことで、全ての業態・四半期で前年比を上回る売上を記録しました。 しかし、売上増加は客単価の上昇 (前年比107.3%)によるところが大きく、客数は2019年の水準まで回復していません (2019年比90.9%)。
出典:外食産業市場動向調査令和5年(2023年)年間結果報告(https://www.jfnet.or.jp/files/nenkandata-2023.pdf)
外食産業は、常に変化する消費者需要や社会的な状況に応じて適応し、革新を続ける業界です。新型コロナウイルスの影響で大きな挑戦を経験した今、外食産業の事業者たちは、テイクアウト・デリバリーの増加やデジタル化の進展など、新たな機会を捉えながら、再び成長への道を歩み出しています。
消費者ニーズの変化に応じる
健康志向や環境意識の高まりに対応したメニューの開発や、サステナブルなビジネスモデルへの転換を検討しましょう。 カロリーや塩分、アレルギー物質の表示にも力を入れる企業が増えています。外食が日常的な行動となった今、健康志向の高まりや、食物アレルギーを持つ人への配慮から、これらの情報開示の重要性が増しています。
飲食店も知っておきたい「食物アレルギー」
【健康寿命と食生活】飲食店の役割とは
【管理栄養士×飲食店】健康意識の高まりを受けて
デジタル化の推進
すでに多くの飲食店が、デジタル化を進め、オペレーションの効率化を図っています。 回転寿司チェーンでは、DX・省力化を推進することで、非接触型サービスを実現。具体的には、スマホアプリでの予約による自動案内、セルフオーダーシステム、セルフレジ、時間制限管理システム、配膳ロボットなど、様々なシステムを導入しています。
人材確保
飲食業界における外国人雇用の重要性が高まっています。特に、特定技能1号・特定技能2号の資格を持つ外国人は、高い技能と日本語能力を持ち、実際に活躍しています。特定技能制度では、技能の資格を得ることで在留資格を取得し、日本で特定の業種に従事することが可能になります。つまり長期的な人材確保が可能となるのです。
歴史から学ぶ外食産業のこれから:まとめ
外食産業は、1960年代以降の高度経済成長期から現在に至るまで、社会の変化と共に進化を続けてきました。ファーストフードの登場、チェーン店の拡大、そしてバブル期の急成長を経て、現在は多様化する消費者ニーズに応える新たな段階に入っています。
日本の食文化は世界的に評価されており、訪日外国人にとって大きな魅力となっています。インバウンド需要の拡大は、観光産業だけでなく、外食市場全体にも恩恵をもたらし、日本経済にとって重要な産業です。 特に、日本食を求める外国人観光客の増加は、外食産業の成長を支える大きな要因です。今後も、消費者の期待に応えながら、日本の食文化を世界に発信し続けることで、外食産業はさらなる発展を遂げるでしょう。
出典 外食産業の歴史を振り返る(https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2410/spe1_04.html#main_content) これからの外食産業(https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2410/spe1_05.html#main_content)