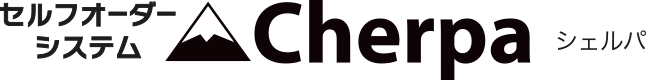2024.06.3
経営
飲食店におけるカスタマーハラスメントの現状と対策

カスタマーハラスメントは「カスハラ」と呼ばれ、年々深刻化しています。カスハラは、従業員に過度な精神的ストレスを感じさせるとともに、通常の業務に支障を来し多大な損失を招くことが想定されます。特に飲食店は、顧客に直接接することが多くリスクが高いと言えるため早急な対策が必要です。 この記事では、飲食店におけるカスタマーハラスメントの現状と対策について紹介します。
---- Table of contents -----
カスタマーハラスメントの現状
カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)は、顧客からの不適切な要求や行為が従業員に対して精神的ストレスを与え、職場環境を害する行為を指します。
厚生労働省が実施した「令和5年度職場のハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年間に顧客等から著しい迷惑行為の相談があった企業の割合は27.9%でした。また労働者に対する調査では、過去3年間に勤務先で顧客等から著しい迷惑行為を一度以上経験したと回答した割合は増加しており、東京都は全国初の「カスハラ防止条例」を制定する方針を示しました。
本来、顧客からのクレームは、商品・サービスや接客態度に対して不平・不満を訴えるもので、それ自体が問題とはいえず、業務改善や新たな商品・サービス開発に繋がるものでもあります。しかしクレームの中には過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつけるものがあります。
また飲食店でカスハラが発生した場合、その場の雰囲気が悪くなり、他のお客様が不快な思いをすることもあります。カスハラにより従業員がストレスを感じることでサービスの質が低下するため、飲食経営者は、従業員を守り大切なお客様への影響を防ぐための対策が求められます。
現場でのクレーム初期対応(カスハラに発展させないために)
現場対応者による初期対応においては、まずは誠意ある対応をしつつ状況を正確に把握し、事実確認をする必要があります。ただし、顧客から暴力行為を受けた場合は、すぐに現場責任者に相談する等、事案を引き継ぎ、従業員一人で対応させないことが重要です。
以下の事項に留意しつつ、まずは顧客の主張を傾聴することが求められます。現場対応の場合は不要なトラブルを避けるため、初期対応の時点で複数名で対応することもよいでしょう。
1.対象となる事実、事象を明確かつ限定的に謝罪する
対象を明確にした上で限定的に謝罪します。
例えば「この度は不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ありません」といったように不快感を抱かせたことに謝り、正確に状況が把握できていない段階では、非を認めたような発言をすることは望ましくありません。非を認めて謝罪するのは、事実確認をして店舗経営者が判断をしたときです。その際も、過失の程度に応じた謝罪をすることが望ましいです。
2.状況を正確に把握する
まずは、今後顧客と連絡が取れるように、顧客の名前・住所・連絡先等の情報を得ます。
次に、顧客が主張する内容を正確に把握することが求められます。顧客から話を聞く際には、途中で発言を遮ることや反論はせず、まずは一通り事情を確認しましょう。相手の話をじっくり聞くことで、顧客を落ち着かせることにも繋がります。
一通り事情を確認した後、顧客が話す内容に不明確なものがあれば確認をし、不足する情報があれば追加で意見をもらい、顧客の勘違いがあれば正しい情報を提供します。また話を聞く際には、常に冷静に穏やかに対応しましょう。
3.現場責任者に情報共有する
顧客から確認した情報は、現場責任者に共有します。正確かつ迅速に状況を把握するため、現場責任者は顧客の要望のみならず、できるだけ事実関係を時系列で整理して報告することが望まれます。
飲食店のカスハラ判断基準
ハラスメントの捉え方は、人によって異なります。 あらかじめハラスメントの判断基準を明確にした上で店舗の考え方、対応方針を統一して従業員と共有しておくことが重要と考えられます。
顧客の要求内容に妥当性はあるか
顧客の主張に関して、まずは事実関係、因果関係を確認します。次に店舗側に過失がないか、または根拠のある要求がなされているかを確認し、主張が妥当であるかどうか判断します。
要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当な範囲か
顧客の要求内容の妥当性の確認と併せて、その要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当な範囲であるかを確認します。
例えば、長時間に及ぶクレームは、業務の遂行に支障が生じるという観点から社会通念上相当性を欠く場合が多いと考えられます。また、顧客の要求内容に妥当性がない場合はもとより、妥当性がある場合であっても、その言動が暴力的・威圧的・継続的・拘束的・差別的などである場合は、社会通念上不相当であると考えられ、カスハラに該当し得ます。
カスハラ行為別 : 顧客への対応例
時間拘束型
長時間にわたり、顧客が従業員を拘束する。居座りをする。
●対応例
対応できない理由を説明し、応じられないことを明確に告げる等の対応を行った後、膠着状態に至ってから一定時間を超える場合、お引き取りを願います。 顧客が帰らない場合には毅然とした態度で退去を求め、状況に応じて弁護士への相談や警察への通報等を検討します。
暴言型
大きな怒鳴り声をあげる、侮辱的発言、人格の否定や名誉を棄損する発言をする。
●対応例
大声を張り上げる行為は、周囲の迷惑となるため、やめるように求めます。侮辱的発言や名誉棄損、人格を否定する発言に関しては、後で事実確認ができるよう録音し、程度がひどい場合には退去を求めます。
威嚇・脅迫型
脅迫的な発言をする、反社会的勢力との繋がりをほのめかす等といった、従業員を怖がらせるような行為をとる。または「SNSにあげる、口コミで悪く評価する」等とブランドイメージを下げるような脅しをかける。
●対応例
複数名で対応し、警備員と連携を取りながら対応者の安全確保を優先します。また、状況に応じて弁護士への相談や警察への通報を検討します。ブランドイメージを下げるような脅しをかける発言を受けた場合にも毅然と対応し、退去を求めます。
SNS・インターネット上での誹謗中傷型
インターネット上に名誉を毀損する情報を掲載する。
●対応例
掲示板やSNSでの被害については、掲載先の運営者(管理人)に削除を求めます。法的手段として、プロバイダ責任制限法に基づき、発信者情報の開示請求を行うことも可能です。これにより、発信者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等の情報を得ることができます。
参照:警視庁 インターネット上の誹謗中傷等への対応(https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/defamation.html)
解決策や削除の求め方が分からない場合には、法務局や違法・有害情報相談センター、「誹謗中傷ホットライン」(セーファーインターネット協会)に相談しましょう。
飲食店におけるカスタマーハラスメントの現状と対策:まとめ
カスハラ対策には、多くの課題があります。ハラスメント行為者が顧客であることで毅然と発言しにくいことや、カスハラの定義や判断基準を明確に定義しづらく、従業員にも周知しにくい等、様々な要因が考えられます。
しかし顧客と従業員の関係であっても、従業員の人格を侵害する行為は尊厳や心身を傷つけ、貴重な人材の損失に繋がるため見過ごすことはできません。 カスハラ対策は、飲食店の経営者だけでなく全ての従業員が理解し、協力して取り組む必要があるでしょう。
厚生労働省:カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(https://www.mhlw.go.jp/content/11921000/000894063.pdf)を飲食店向けに省略・加工して作成