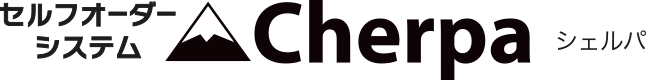2024.07.1
接客
「ハラルフードとは?飲食店が知っておきたいムスリム観光客の対応

マレーシア、インドネシアをはじめとしてムスリムの多い東南アジアからの観光客が増加しています。それに伴い国内の観光・飲食業界では「ハラルフード」という言葉を聞くようになりました。この記事では、飲食店が知っておきたいムスリム観光客の対応を解説します。
---- Table of contents -----
ムスリムとは、イスラム教の信者
ムスリムとは、世界三大宗教のひとつイスラム教の信者を指し、世界に16億人以上いると言われています。世界最大のムスリム人口を持つ国はインドネシアで総人口の9割近く、マレーシアでは国の宗教がイスラム教とされています。
ハラルフードとは、ムスリムが食べる食品や料理
ムスリムは、イスラム教の教えに基づいて生活をしています。生活全般に「ハラル(ハラール)=許された行為・物」と「ハラム=禁じられた行為・物」という考え方に基づく規範があります。
ハラルフードとは、イスラム教の教えに沿って食べることが許された食品や料理のことを言います。特定の食品や料理というより、禁じられたハラム以外がハラルフードとされます。
ハラム:禁じられた物
豚・豚由来品
イスラムの教えでは、豚肉は口にしてはいけないという決まりがあります。豚の内臓、皮膚、体毛や豚由来成分にも注意が必要です。
注意すべき具体例
豚肉を使用した加工食品(例:ベーコン、ソーセージ)、豚のエキス、油脂(例:豚骨ス—プ、ラード)、豚の内臓(例:モツ)調味料、添加物等に含まれる豚由来成分(例:乳化剤、ショートニング、ゼラチン、コラーゲン)
アルコール
イスラムの教えでは、酩酊する酒(アルコール飲料)を口にすることは避けるべきとされているため、多くのムスリムは酒(みりんを含む)を口にしません。中には醤油等の調味料に含まれる微量のアルコールについても口にしないムスリムもいます。 調味料に微量に含まれるアルコールや、エタノール(酩酊する酒ではなく消毒用のもの等)を避けるべきかについては意見が分かれます。
ハラールではない動物性食材全般
イスラムの定める適切な「と畜方法」で処理された肉(ハラール肉)以外を口にすることは避けるべきとされています。豚と同様、ハラール肉以外に由来する食品や食品添加物等に含まれる成分も避ける必要があります。
【豚・豚由来品以外の肉について】
イスラム教の教えに従って適切に屠殺された牛や鶏などの肉は、ハラルフードとされます。日本国内でハラール認証を取得した食品を製造・販売する企業もあり、イスラム教の教えに従った方法で食品を製造しています。
また、日本国外から輸入されたハラール認証を取得した食品も利用されています。ブラジル産等の鶏肉、オーストラリア産等の牛肉の場合はハラル認証がある場合が多いようです。
これらの食品は、イスラム教の教えに従った方法で製造・屠殺されており、日本のムスリムコミュニティにとって重要な食料源となっています。
その他注意点
調理の過程でムスリム向けではない食材が混入してしまうことを懸念するムスリムもおり、調理器具だけでなく調理環境全体を気にするようです。しかし、きちんと調理器具や食器を洗っていれば問題ない、という声は多いです。
ムスリム向けではない料理・飲酒の様子が見えないように個室利用、店舗の一部をパーテーションで区画するなどの対応を望む声もあるようです。

飲食店のハラルフード対応
ムスリムの習慣には地域差や個人差があり、ムスリム向けの対応に統一の基準はありませんが、「ハラール認証」という制度があります。これは、イスラム教と食品衛生の専門家が、特定の食品等をハラールであるかどうか判断し保証する制度です。しかし、これには厳しい基準が設けられており、よほどの必要性がなければ取得は難しいでしょう。
しかし、多くのムスリム観光客は普段日本で食べられているような料理を食べたいと考えており、ムスリムで認証まで求める人は少ないということです。
そこで、ハラール認証対応ができない場合でも、原材料などの情報提供を適切に行い、ハラールであるか否かの判断はムスリムに委ね、おもてなしをする考え方もあります。
1. ムスリムフレンドリー
部分的にはムスリム対応を行うレベルを「ムスリムフレンドリー」といいます。以下は一例です。
食材は全てムスリム対応
キッチンはハラール専用ではないが調理器具・食器はハラール専用
上記の対応をする一方で、アルコールは販売
2. ノーポーク・ノーアルコール
ムスリム対応に必要最低限の取組を行います。
豚・豚由来品を除く
酩酊する酒(アルコール飲料)・アルコールを含むものを除く
3. 情報開示
情報開示• ムスリム対応の可否を判断できるように情報を発信します。
ピクトグラム・自社ポリシーの策定による判断材料の提供
多言語メニュー
ムスリムが使用する言語は多岐にわたりますが、東南アジアの国々では、英語が公用語または準公用語として広く使用されている場合が多いため、ムスリム観光客の中には英語を理解し、コミュニケーションを取ることができる人が多いと考えられます。
英語をはじめ複数の標準言語切替が可能なセルフオーダーシステムを導入することで、スムーズにメニューの情報を提供できます。
飲食店のムスリム対応事例
【店舗独自で確認した材料を用い、ノンポーク・ノンアルコールメニューを提供】(京都府・湯豆腐)
完全ノンポーク・ノンアルコールのメニュー2種類を常時提供できるように準備している。
使用している調味料はハラール認証が付いたものではないが、アルコールが全く含まれていないことを店舗で確認して使用してる。
厳格なムスリムにとって完全な対応ではないため、事前に予約を行う旅行会社等に対応内容を伝え、問題が無いかを確認している。
【ムスリムのお客様来訪時にアルコールが含まれないよう配慮】(岩手県・そば)
食のバリアフリーの一貫としてムスリムのお客様向け対応も行っている。
ムスリムのお客様の数は多数ではないため、特別な食材や調味料をムスリム向けに用意することはしていないが、そばつゆから酒を抜くなどして、既存の材料の中で配慮して提供。
【少ない投資で対応可能な範囲ながらも、情報提供によりムスリム旅行者が安心できる対応を実施】(岐阜県・日本料理)
外国人旅行者に人気の観光地周辺に位置しており、数年前から周辺でムスリムの旅行者を度々見かけるようになってきていたため、今後の増加を見据えてムスリム対応を始めた。
ムスリム対応を開始する際には、インターネットでの情報収集に加え、地域のムスリム受入活動と連携し、国内先進地域を視察、近隣のモスクからの指導も受けた。
ムスリムのお客様向けに、ノンポーク・ノンアルコールのメニューを準備。
現時点ではムスリムのお客様が少ないため、投資を要する調理方法の区別までは行っておらず、その旨情報提供をして安心して食事してもらえるようにしている。
礼拝を希望するお客様には、施設内の個室を開放して、マットやキブラを貸し出すほか、清浄のために桶とペットボトルを貸し出して対応。
ハラルフードとは?飲食店が知っておきたいムスリム観光客の対応:まとめ
ムスリム観光客は、大都市だけでなく地方エリアにも訪れています。そのため日本中、どの地域にもムスリムの方が訪れる可能性があります。飲食店が積極的にハラルフードを扱わないとしても、ムスリムを知り理解することがおもてなしに繋がります。
イスラムの教えの解釈やその実践方法は宗派や国・地域、文化、個人によって異なります。何が「ハラール」であるかは、ムスリム旅行者自らの判断に任せましょう。対応できること・できないことを伝え、ムスリム旅行者自らが選べるようにすることが重要です。
観光庁:ベジタリアン・ヴィーガン/ムスリム旅行者おもてなしガイド(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001740443.pdf)を加工して作成