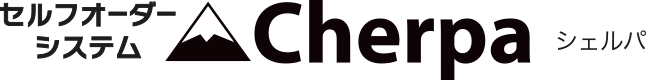2025.04.7
経営
DXへの一歩を踏み出そう|飲食店のデジタル化推進マニュアルをわかりやすく解説

飲食店経営を取り巻く環境は、円安による物価高騰や原材料費・燃料費の高騰に加え、少子高齢化による深刻な人手不足に直面しています。
消費者の情報収集や購買活動はスマートフォン中心へと大きく変化している中、政府はデジタル社会の実現を推進しており、デジタル庁の設立やIT導入補助金など、事業者のデジタル化を支援する動きが活発です。
この記事では、このような背景を踏まえ、飲食店がデジタル化によってどのように経営課題を解決し、生産性を向上させていけるのかを、厚生労働省のデジタル化推進マニュアルを元に、具体的かつ分かりやすく解説していきます。
---- Table of contents -----
飲食店経営の現状と課題
飲食業は以下のような多くの課題を抱えています。
変動費の高騰
原油高や円安による燃料や原材料費の高騰は、飲食業に大きな影響を与えています。
新規顧客の開拓
高齢化に伴い、商圏内の顧客は減少傾向にあり、新たな顧客層の開拓が急務となっています。
顧客単価アップ
インフレが進む可能性があり、単価向上も重要な課題です。
労働力と後継者不足
労働力人口の減少により、従業員の確保がますます困難になっています。後継者不足も深刻な問題です。
その他、市場規模の減少、都市部と地方の格差、店舗施設の老朽化といった課題も存在します。 これらの課題に対し、従来のやり方だけでは限界が見えてきています。そこで注目すべきが、デジタル技術の活用です。
なぜデジタル化が必要なのか?
デジタル技術の進化は、まさに追い風です。企業は生産性向上に向けてデジタル技術を活用し、経営課題の解決に取り組んでいます。厚生労働省も、生衛業におけるデジタル化のメリットとして、労働生産性の向上を強調しています。
労働生産性とは、「投入資源(総労働時間)」に対する「算出成果(粗利)」で表されます。
労働生産性 = 粗利(売上-原価)÷ 総労働時間
そして、労働生産性を向上させるためには、以下の3つの方法があります。
1.売上の増加
2.原価の削減
3.総労働時間の短縮
デジタル化は、これら3つのすべてに貢献できる可能性を秘めているのです。「IT導入補助金」をはじめとする様々な補助金や助成金の申請においても、この生産性向上の考え方が重要なポイントとなります。
飲食店におけるデジタル化のメリット
では、具体的にデジタル化によってどのようなメリットが得られるのでしょうか。
1.労働時間の短縮と効率化
給与計算、勤怠管理、会計処理などのバックオフィス業務を自動化することで、大幅な時間短縮が可能です。注文受付や会計をセルフ化することで、従業員の負担を軽減し、人手不足の解消にも繋がります。
2.売上増加の機会創出
POSレジのデータを分析することで、売れ筋商品や顧客の嗜好を把握し、効果的なメニュー開発や販促活動に繋げることができます。ホームページやSNSを活用した情報発信により、新規顧客の開拓や認知度向上を図ることができます。オンライン注文やデリバリーサービスの導入により、新たな販路を拡大できます。
3.原価の削減
POSレジによる在庫管理の最適化により、食品ロスを削減できます。仕入れ情報をデジタル化することで、より効率的な調達が可能になり、コスト削減に繋がります。
4.顧客満足度の向上
顧客データを活用したOne to Oneマーケティングにより、顧客一人ひとりに合わせたサービス提供が可能になります。オンライン予約や事前決済の導入により、顧客の利便性を向上させることができます。
5.データに基づいた経営判断
POSレジや各種システムから得られるデータを分析することで、勘や経験に頼らない、客観的な根拠に基づいた経営判断が可能になります。売上、コスト、資金繰りなどをリアルタイムに把握し、迅速な意思決定に繋げることができます。

デジタル化の進め方
デジタル化をどのように進めていけば良いのか、その手順を見ていきましょう。
フェーズ1:事前調査
まずは、店舗の情報を事前に収集します。経営状況(売上・利益、コスト構造、人員・人材の情報等)に加え、店舗・店主のありたい姿、かなえたい目標を明確にすることが重要です。インターネット上の情報や財務指標だけでなく、従業員へのヒアリング、店舗のオペレーション調査を通じて、店舗の実態(ヒト、モノ、カネ)を包括的に明らかにします。
フェーズ2:現状分析・課題抽出
フェーズ1で収集した情報をもとに、店舗の現状を分析し、課題を特定します。売上面、財務体質・コスト面、業務プロセス面、人員・人材面など、多角的な視点から現状を把握します。課題が複数ある場合は、重要度や優先順位を設定し、取り組むべき課題を整理します。
フェーズ3:取組計画策定
フェーズ2で抽出した課題に対して、解決策を考え、どのように取り組むかを検討して、計画を策定します。
例えば、バックオフィス業務が煩雑な場合は、財務管理システムや勤怠管理ソフトなどを導入する、自店舗の認知度が不足している場合は、ホームページやSNS等の開設及び発信を行うといった対策が考えられます。
フェーズ4:デジタルツール導入
フェーズ3で策定した取組計画に沿って導入を進めます。各種デジタルツールの調達要件に基づき、外部の協力先ベンダーを評価しながら、パッケージ、クラウドサービスの導入など各種デジタルツールを選定します。
例えば、顧客接点においてはセルフオーダーシステムを導入したり、売上・利益計画や労働時間の削減を見越し、投資対効果を見積もり、顧客や従業員の目線を踏まえて導入を実行します。
フェーズ5:デジタル化定着
デジタルツールを導入しただけで終わらせず、定着に向けて取り組みます。
デジタルツールが定着すると、店舗には多様な定量データが蓄積され、リアルタイムに確認できます。データに基づく意思決定のスパイラルはデジタル化のゴールとも言えます。
デジタル化定着に向けて重要な3つの視点(①失敗の寛容、②アップデート、③データ活用)を意識して取り組みましょう。
-
失敗の寛容
先んじて挑戦し、失敗からも学び、チームの成長につなげます。 -
常にアップデート
技術の進化は速いため、自分自身も常に新しい情報を取り入れ、更新し続けます。 -
データ活用
蓄積されたデータは、集客や業務効率化に役立つ情報源となります。
経営課題解決に向けた具体的なデジタル活用

ここでは、飲食業の課題に対し、どのようなデジタル活用が考えられるかをご紹介します。
1:POSレジを分析と管理に活用
POSレジは、「いつ、何が、いくらで、いくつ、誰に、またはどんな人に、販売されたか」が自動的に登録・蓄積されるシステムです。店舗の経営分析や販売促進に必要なツールであり、飲食業デジタル化の入口と言っても過言ではありません。導入する際には、「経営課題や業務課題の解決を支援できる機能」を持っているかに重点を置きます。
セルフオーダーシステムや、事前注文・決済システム、ECサイトやデリバリー、キャッシュレス端末、会計システムなどと連携させることで、店舗運営における必要なデータを体系的に集積し、PDCAサイクルを回すことができます。
2:バック業務にデジタルを活用し、付加価値が高いフロント業務に時間を使う
デジタル化は、繰り返し作業の時間短縮(ペーパーレス化、財務会計システム、人事管理システムなど)、勘や経験など俗人化からの脱却(POSレジ、顧客管理システムなど)、固定化した業務場所からの脱却(クラウド化、オンライン化など)に効果を発揮します。バック業務のデジタル化で創出された時間を、付加価値を生むための取り組みや、付加価値の高い業務に使うことができます。
3.勤怠管理や会計管理にデジタルを活用する
勤怠管理や会計管理にシステムを導入すると、毎日・毎月・毎年の記録が自動的に蓄積され、集計できるようになります。売上金の自動取り込み、請求書やレシートの自動取り込み(写真撮影)、売上・コスト・資金繰りの一目でわかるレポート機能など、経理業務・人事労務の負担を大幅に軽減できます。
削減できた業務時間を、接客や教育、メニュー開発、サービスの拡充、お店のプロモーション、従業員のモチベーション向上など、顧客や従業員により喜んでもらえる業務に集中させることができます。
課題を明確にし必要な対策を検討
自身の店舗の経営課題と照らし合わせ、必要な課題に焦点を当ててデジタル化に取り組みます。
変動費管理の工夫
POSレジを活用したメニュー分析による食材の見直し、需要予測に基づいた仕入れによる食品ロス削減、クラウド会計ソフトによる経費の一元管理と分析などが考えられます。
新規顧客の開拓 + 顧客単価増
Googleビジネスプロフィールを活用した情報発信、ホームページやSNSによる店舗情報の発信、キャンペーンの告知、オンライン予約システムの導入による予約の簡便化、顧客データ分析に基づいたターゲットを絞った情報発信、POSレジを活用した顧客分析による嗜好に合わせたメニュー提案(クロスセリング、アップセリング)、ポイントシステムや会員制度の導入によるリピーター育成、オンライン注文・デリバリーサービスの導入による新たな顧客層へのアプローチなどが有効です。
従業員の確保難
勤怠管理システムや給与計算システムの導入による業務効率化と従業員の負担軽減、オンラインでの求人活動や情報発信、コミュニケーションツールの導入による従業員間の連携強化などが対策として挙げられます。
DXへの1歩を踏み出そう|飲食店のデジタル化推進マニュアルをわかりやすく解説:まとめ
デジタル化は、決して難しいものではありません。課題を明確にし、一つずつステップを踏んでいくことで、生産性向上、経営改善へと繋がります。
補助金などの支援策も積極的に活用しながら、この変革の波に乗り、デジタル化を「攻めの経営」の強力な武器として、未来を切り開いていきましょう。
厚生労働省:デジタル化による 生産性向上のすすめ(https://www.mhlw.go.jp/content/innsyoku2024.pdf)を加工して作成